50代おじさんの昼ごはん・睡眠など
サンドイッチが定番だった僕の昼ごはんが、最近大きな変化を見せております。
ごはん食に切り替わったのです。例えば、昨日はこんな感じ。

(時計周り)十六穀米、キムチ、サバ缶、納豆、味噌汁……塩分過多ですね
昨日と書きましたが、ほとんど毎日同じような昼ごはんを食べています。卯の花やおひたし、卵焼きなどがプラスされたり、キムチや納豆がない時もありますが基本的に同じです。おじいちゃんが食べてそうなごはんですね(笑)。
そんなわけで今日は、50代おじさんの昼ごはん、1日の生活についてのつまらない話でございます。
Habit Stacking
来年(2026年1月)で52歳となるわたくし、aw。
娘の誕生をキッカケとして、完全夜型から朝型の生活に移行し、アルコールを控え(一時期は完全に断酒していた)、若いころやっていたジョギングを再開、そしてお昼ごはんの和食化と、徐々にですが健康的な生活へとシフトしてきました。
会食の席などで僕のふだんの生活について話をすると、ずいぶんと極端に暮らしを変えたように思われるのですが、そうではありません。何年もかけて徐々に変えてきました。自己啓発用語で言うところのHabit Stacking(ハビット・スタッキング)※1、習慣化しているいつもの生活に少しずつ新しいものを重ねていくという方法です。もちろん、意識を高くもって生活改善に取り組んできたわけではなく、結果的にそうなったということなのですが。
娘が寝る時間(午後9時)に自分も寝るようになっただけだし、夕食時にビールを飲むと娘を風呂に入れたり寝る前の本読みが億劫になるのを避けるためにビール飲まなくなっただけだし、親世代が足腰から悪くなっている様子を見て恐怖し走りはじめただけ。
昼ごはんは、自炊できる環境を活かしていかに簡単に昼ごはんをつくれるか(そしてそれが肥満予防、HbA1cの管理、軽度の脂肪肝改善につながれば尚良し※2)という手抜き発想ではじめました。サンドイッチは意外と手間がかかるし、たくさん食べないと腹持ちが悪いので毎日だと……という事情もありました。
今食べている昼ごはん、上の写真を見ると分かりますが、レンチンするか、開封するだけで食べられるものばかり。加えて、せっかく自炊するんだったら、体に悪いとされているもの=野菜/果物ジュース、グラノーラ、ウインナーやハムなどの加工肉、揚げ物、ぶどう糖果糖液糖が含まれるもの=をできるかぎり排除してみよう(代替となるような食べ物がとびきり高くつかなければ)という感じです。
サバ缶はまとめ買いすると150円くらいと激安ですし、サバ缶とスタメン争いしている鶏のムネ肉も比較的安価。納豆やキムチなどを含めても一食あたり350円くらい。コメが一番高いのはご時世ですかね。
ただ、安いから早いから体にも良いからと言ってこれを家族に無理強いすると家庭崩壊の原因となりかねませんので、昼ごはんだけに留め、夜は食べたいものをみんなで食べています
と言いつつ、娘と二人で昼ごはんを食べる時は、完全に僕の嗜好に合わせておりますが(笑)。

ある週末のお昼ごはん
キッカケは色々あるのでしょうが、こうして人の食べるものって変わっていくんですかねぇ……。
寝る時間から逆算して1日を組み立てる
僕は自分の睡眠に関する過去の失敗経験から(いつか書きます)、娘に対して一番大事なのは寝ることだ」と、ひたすら伝えてきました。一日の行動を就寝開始時間から逆算して予定を立てるように話し、「寝ること以上に大切なことはない」「成績を上げたかったらたくさん寝ろ※3」「旅行とか友だちとのお出かけとか、楽しい予定をキャンセルしたくなかったら早く寝ろ」「とにかく早く寝ろ」と。
そう言ってきた手前、手本となるべき親が夜更かし生活するわけにはいきません。トム(妻)は元来眠るのが好きで、言われなくても早く就寝するのですが、もともと僕は筋金入りの夜型人間なので、夜9時に寝るというのはある種の挑戦なのです。最近はすっかり定着してきましたが。
平日、娘は9時間睡眠、僕は走るために4時過ぎに起きるので7時間睡眠です。
1日のうち7時間寝ているということは、起きていられるのは17時間。その17時間をこんな感じで割り振って、ここ最近の僕の生活は回っております。
| 睡眠 | 7時間 |
|---|---|
| 朝ごはん | 30分 |
| 昼ごはん | 40分 |
| 夕ごはん と食後の団欒 |
1時間30分 |
| 仕事 | 7時間30分 |
| ジョギング | 45分 |
| 家事 | 1時間 |
| 新聞・読書 | 2時間 |
| 英語の勉強 | 1時間 |
| 風呂 | 45分(朝と夜の合計) |
| 犬散歩 | 30分(夕方のみ) |
| その他 | 30分 |
当然のことながら、毎日同じように1日が流れていくわけではなく、この表にはない何かしらやるべきことが生じます。それを吸収するために「その他」を設けていますが、30分では収まらないこともよくあります。よくあるところで言えば、仕事が終わらないとかですね。そういう場合は優先度の高くない読書を割愛したり(涙)、夕食の片付け当番をトムや娘に代わってもらったりとやり繰りしています。
ちなみに、格闘技を観戦したいとか観たい映画がある場合は、日曜日だったり、仕事の密度が低い時に見たりしていますね※4。このブログもそんな感じで書いてます。
とにかく、寝る時間を決めると「今日はちょっと夜更かししてYouTubeでも見よう」とか「おっと、うっかりSNSをダラ見したら夜中になっちまった」みたいなことがなくなります。この誘惑に負けそうになった時は「それは朝早く起きてもやりたいことか」と自問自答します。たいていは「NO」です。
他人にしてみればこれがストイックな生活に見えるようなんですが、これが苦行になってしまうと絶対に続かないので無理のないように計画することと、何かの用事でたまにそれが崩れても気にしないことが大切な気がします。
・・・
というわけで、50オヤジの生活についてでした。
- 「Habit Stacking 人生を大きく変える小さな行動習慣」S・J・スコット(著)、和田美樹(翻訳)
- 現在も特段悪いわけではありませんが、HbA1cと軽度の脂肪肝は少し前に指摘されていたので、今も気にしつつ生活してます。
- YouTube「【子どもの睡眠】“脳”が育たない?寝不足は一生のハンデに…「日本の赤ちゃんは就寝時刻が遅い」親の生活リズムが影響【久保田智子のSHARE#31】」
「【子どもの脳育て】脳の発達は順序が大切/カギは「脳の発達3ステップ」「3つの神経伝達物質」/過干渉の原因は親のストレス/グロース・マインドセットに育てる方法」(24:54あたりの専門家の発言)。この動画とは別に、出典は調べ中なのですが(見つかり次第掲載します)幼い頃に十分に睡眠をとっている子供(A)は、そうでない子供(B)と比べると、中学から高校以降の成績上昇率が高まり、それ以前はBがAを成績で上回っていても逆転するケースが多いという研究があるそうです。Bの子供は睡眠時間を削って勉強をするなどし、その時のテストでの成績等は高まるものの、睡眠不足にyほって脳自体の発達が十分に促進されない可能性があるようです。他方、Aの子供は十分な睡眠で脳が発達するので、脳の発達に従って成績が向上するとのこと。親が近視眼的にその時の成績だけに注目するのではなく、長い目で子供の健康と生育を第一に考えることが、学業の向上にも寄与するということですね。 - 一番好きなUFCは時差の関係で、たいてい日曜日の午前中に配信されているので、娘とのんびり観戦することが多いです。



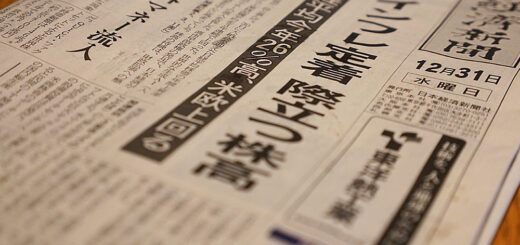


























俺も生活リズムや食事は随分変化したなと実感してる。真似してみようと思ったこともあったけど流石に俺には9時消灯はなかなか難しい。
今度のキャンプでもサバ缶食おうか笑
午後7時までのお店やりながら午後9時に寝るのは厳しそうだな! 結局何時間眠るかと、起きている時間になにするかってことが重要だから、俺みたいに朝4時に起きる必要がなければ11時に寝て朝6時に起きれば7時間睡眠でいい感じなんじゃない? できればもう1時間寝たいところだけど笑